ストレスをAIで見る方法
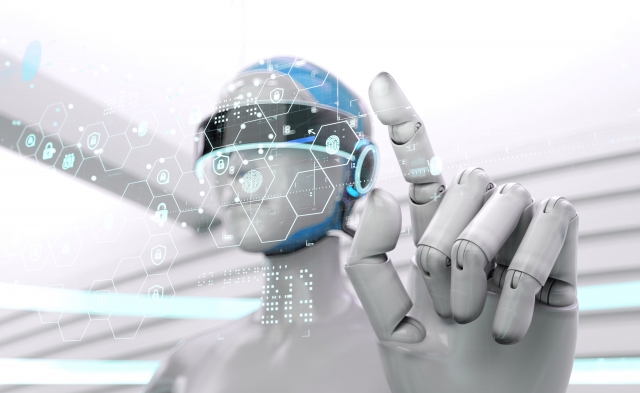
おはようございます。
アシストユウの小幡です!
今日もお越しいただき、ありがとうございます。
今回は、「AIでストレスを見つけた後、どう対応するか?」というテーマで、
前回ご紹介した“ストレスの可視化AI”を、実際にどんな現場で使って、どんなふうに対応しているかというお話をしていきたいと思います。
ストレスは可視化できる
AIが「異常かも?」と判断したあと、どうする?
AIで人物のストレスレベルを検知した場合、
たとえば、映像上で「赤」や「警告マーク」などの形で表示されます。
でも、ここで大事なのは、その結果をどう扱うか?です。
AIはあくまで「可能性」を提示してくれるもので、
最終的に判断し、行動するのは“人間”です。
だから、当社はいつもこう伝えています。
「AIは“気づくきっかけ”をくれるツールであって、すべてを決める機械じゃない」
つまり、「アラートが出た=即通報」ではなく、
「ちょっと変化がある人がいる」という“気づき”を与えてくれるのがAIの本当の価値なんです。

実際の活用例:離島の港湾現場でのストレスチェック
ここで、実際にあった活用例をご紹介します。
当社が手がけている移動式ネットワークカメラ「モニタリングミックス(MICS)」には、
このストレス可視化AIを搭載することができるんですが、
ある離島の港湾工事現場で、実際にこのAIを導入したことがあります。
この現場は、医師が毎朝現場入りして作業員の体調をチェックするというルールがあるような、かなり厳格な安全管理の下で運営されていました。
そこでMICSを使って、作業前の集合時にカメラで全員を撮影し、AIでストレス傾向をチェック。
医師がその映像を見ながら、「今日はこの人に少し声をかけてみよう」と判断する、
“判断の材料の一つ”としてAIを使っていただきました。
これがすごく現実的で、理想的な使い方だったなと僕は思っています。

“人を支えるAI”であって、“人を置き換えるAI”ではない
こういう使い方の中で感じたのは、
AIはあくまで「サポート役」であり、現場の判断や行動をサポートする“もう一つの目”のような存在だということ。
何かに気づく。
何かに注意を向ける。
その最初の一歩をAIが担って、
最終判断は現場の人がする──それが一番自然な形なんです。
まとめ:気づける仕組みがあること、それが本当の安心
ストレスの可視化AIは、「犯人を見つける道具」ではありません。
“大丈夫ですか?”と声をかけられる環境を作るためのツールです。
MICSはこれからも、こうした「技術と人の安心がちゃんとつながる仕組み」を大切にして、
ただの監視ではなく、“守るための見守り”を広げていけたらと思っています。
次回は、「熱中症も検知できるの?」についてお話ししていきますね。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました!
現場の皆さん、AIってなにがあるの?など疑問があれば、
是非お問い合わせください。
月額1万円~使用したいという方はこちら
https://assistyou-m.com/mics/ai_kids/
https://www.facebook.com/yuuki.obata?locale=ja_JP
上記より友達登録の上、メッセンジャーにてDM、メッセージをお送りください。
現場からは以上です。
追伸
アパレル・グッズやってます。絵本制作の費用にあてられます。
https://yukidrearoom.thebase.in
応援したい人用 絵本制作の費用にあてられます。
https://community.camp-fire.jp/projects/view/322931



